お寺に提案できること
名古屋別院さんの境内に納骨堂を設計させて頂いて半年が経過しました。設計当初から納骨堂と言う機能を作るのではなく、地元の拠り所となる「場所」を提案しようと思っていました。なので私自身の設計は納骨堂ではなく、テラスの計画とそのテラスの存在意義と生かし方だと感じていました。そして、その生かし方を出来る限りお寺の「肉体的」「金銭的」負担を少なくして続けていけることを提案したいと思っていました。まずその第一弾として境内でマルシェを開催しました。トップのある画像はその時の一コマとなります。
マルシェの提案
テラスを計画し、そこを核に何かイベントを催すことを建築中に同時に考え、最近よくあるマルシェを考えました。ただ、私自身マルシェを主催したことも、出店したことも無いので、当時は月に2回はどこかのマルシェに行ってみようと沢山のマルシェに行きました。併せて主催者・出店者向けの勉強会にも参加し、自分なりに客側・ビジネス側から見てみました。そして24年9月のマルシェを終えて感じたことは、続けることの大事さとイベントをしたいと思う依頼者側の熱量の重要性でした。その中でも一番感じたことは、まずは自分自身(依頼者も)がワクワクして楽しいか?でした。決してイベントの善し悪しは出店者の数やマルシェの規模などでは全く関係ないなと感じました。そしてマルシェのようなイベントも今では一般的になり、場所が変わっても出店者の顔ぶれに変化がなかったり、イベントの成功よりどれだけ売れたかと言うことに重きが置かれたりするように思うイベントもあります。これからは自身の少ないながらの経験とお客さん側の目線を念頭にご提案できればと考えています。
建築士として設計以外に提案できること
例えばレストランを計画するとき、明日オープンと言ったときに、携わるスタッフ以外の事は用意しておかなくてはなりません。例えばお皿やシルバーもそうですし、テーブルで積算するのであればマネープレートも必要です。郊外の路面店なら傘立ても必要かもしれません。そういった細部に目を届かせることが出来るかどうかで、建築全体の質も向上させることはできます。決して上質で高価なものをセレクトするわけでもなく、全体との調和がとれているだけで全然違います。

こちらは傘立てとして購入した陶器です。東海エリアは焼き物の産地が多数あります。瀬戸焼・七宝焼・常滑焼・美濃焼などです。今回は岐阜県の土岐と多治見に行って見つけてきました。
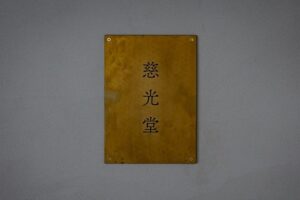
こちらは納骨堂入口の行燈サインです。真鍮製で経年変化を見て頂きたいと思っています。今回の計画ではテラスも含めて極力自然のものを使い、その経年を楽しんでいただきたいと思っています。木・土・石・真鍮・鉄などです。

行燈が灯るとこんな感じになります。10年後には木は少し焼けて色に赤みが増えてくると思います。石は少し汚れるでしょうし、真鍮は黒ずんでくるでしょう。50年後は木はこげ茶になり、石や真鍮はさらに汚れ黒ずんでくるでしょう。それも含めて境内の景観になることを考えました。お寺の主役は新しく建てた納骨堂ではありません。名古屋別院さんで言うと戦後建てられたインド様式の本堂や江戸時代の鐘楼、樹齢のある木々も含めた境内全体が主役です。すでに経年変化のある者たちと一緒に年を経て、新しい納骨堂も名古屋別院の歴史になって頂きたいと思います。
名古屋別院さんで携わったこと
建築以外ではテラス全体の景観、納骨堂内の椅子と通路の腰掛、納骨堂のネームプレートとインターホンカバー、傘立て、エントランスの飾り石、ロゴマーク、イベント企画そして納骨檀の扉のデザインです。

こちらは入口正面の飾り台です。三河産の御影石を山で探してきてなるべく加工を少なくして切り出したままで使っています。これは愛知県岡崎市の石屋大島組と山に探しに行きました。

こちらは先ほどの飾り台の上部からつるしているペンダント照明です。

こちらは納骨室のご本尊前でお経などをあげる際に必要になるフロアスタンドです。ペンダント照明とフロアスタンドはどちらも真鍮製です。

こちらはテラスに入るところに置いてある侵入禁止の柵となります。カラーコーンでは味気ないのでコンクリートの洗い出しの受けと竹をバーとして使いこのようにしました。これはテラスを作って頂いた櫻井さんの提案となります。
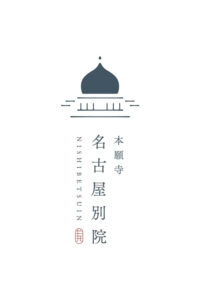
こちらは名古屋別院さんのロゴマークとなります。本堂のインド様式をモチーフに作ってあります。製作はふくろう経営デザインの神谷さんです。神谷さんには納骨檀の扉のデザインもお願いしました。
ひとつひとつは大したことではないですが、全体として見たときに違和感なく統一感が出たと思います。そして、それが建築自体の完成度も上げてくれたと思っています。そして、それらは私個人の力ではなく沢山の職人、デザイナーさんのセンスと能力があっての事です。出来るだけ既製品に頼らず知恵とセンスで今回の名古屋別院さんの仕事を完成させようと言う当初の想いがある程度ぶれずに最後までたどり着いたの様におもいます。
